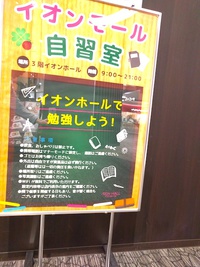2017年09月06日
青年育成ってなんだろうと、本気で考えたけど、なに?な話し
雑記になりますが、青年育成についておもうことを書いておきます。
内閣府の青年育成プログラムの地方プログラムを和歌山ですることになりました。
私の専門は障害者福祉、健康社会学、ファシリテーションといった分野なんで、青年育成はちょっと暗いところ。
で、色々調べています。
青年育成ってなんだろう。
そのなかで、これはどういうことなんだろう??・・・と疑問に思うことが多々でてきました。
青年にかかわるサポートは障害者や高齢者に比べてかなり手薄です。
それは、日本の制度は、高齢者も障害者、貧困者といった、生活の中で困難を抱えた人しか対象としていないからです。なにか、困った状態にあったり、なったりしたときに、カテゴリー化され、そしたら制度の対象となります。
いわゆるセーフティネットです。
(カテゴリー化と言えば、難しく聞こえますが、たとえば障害者手帳の取得とか、銀行預金額がいくらで年収がいくらとか、何歳以上であるとか、そういったヤツ。)
65歳以上になれば高齢者と言われますし、75歳以上で後期高齢者(例外有)とか言われますし、精神障害者保健福祉手帳を取得すれば精神障害者となります。(不思議ですね。病気があっても手帳をもっていないと制度の対象にならなかったりします)
その点、青年(ここでは主に12歳〜39歳ぐらいを想定)は、ひきこもりや貧困というカテゴリーに当てハマらなかったら、なんの制度もうけれんというわけです。セーフティ機能じゃないから。
なので、学校以外の青年育成の取り組みは、NPOや有志団体、各自治体によるところが多いかと思います。
なので、ばらつきが大きいです。
調べれば調べるほど、ざっくざっくと、いろいろ出てきます。
難しんですが、やはり青年育成って大切だなと思いました。
就職するも、すぐやめてしまう。
集団に入れない。
地域との交流の断絶。
それが、将来的に貧困や病気などのリスクをあげることにつながっています。
青少年の時って、意外に問題が無いようにみえたりするんですが、この時の学びや活動が、本人だけでなく、その地域にとっても大切だということが見えてきました。
問題は即席的にできあがらないみたいです。
私は、問題は個人にではなく、環境と、環境との相互作用にあると考えています。
例えば、仕事をすぐやめてしまう、という問題があったとしても、それは辞めてしまう人個人に全責任があるとは思いません。
現在の日本で求めれれている青年像はどんなものでしょうか。
経験的な所感になってしまうが、それは青年個人の本人の自主性が強く求められ、経済的自立の過度な強調ではと思います。
そういった強いプレッシャーに押し込まれ、選択性を失なっていることが、青年育成の問題ではないだろうかと、思うようになりました。
また、小さい頃から消費する文化に浸っているため、「消費者としての主体」となってしまうことも課題かと思います。
コンビニに行けば、お金さえ持っていれば子どもでもお客様として扱ってくれます。
(私は小さいこと、駄菓子屋にお菓子を買いに行ったときに、うっかり扉の敷居を踏んでしまいました。
そしたら、おばちゃんにめちぇめちゃ怒られました。)
スマホやパソコンで、遊びのニーズは満たされてしまう。
いつも、消費者としての生活なんですね。
何かを変えたり、創り出していったりする力が奪われていると思います。
なので、今後大切なのは、道をはみ出し、楽しむことが出来る若者の主体の形成と、それを受容できる環境整備ではないかと思っています。
(決して、経済的な教育を否定しているわけではなく、選択肢の狭まりが問題なのではと言いたいのです)
これかれら、もうすこしヒアリングを通じて、充実したプログラムができるように、コツコツやっていきたいと思います。
内閣府の青年育成プログラムの地方プログラムを和歌山ですることになりました。
私の専門は障害者福祉、健康社会学、ファシリテーションといった分野なんで、青年育成はちょっと暗いところ。
で、色々調べています。
青年育成ってなんだろう。
そのなかで、これはどういうことなんだろう??・・・と疑問に思うことが多々でてきました。
青年にかかわるサポートは障害者や高齢者に比べてかなり手薄です。
それは、日本の制度は、高齢者も障害者、貧困者といった、生活の中で困難を抱えた人しか対象としていないからです。なにか、困った状態にあったり、なったりしたときに、カテゴリー化され、そしたら制度の対象となります。
いわゆるセーフティネットです。
(カテゴリー化と言えば、難しく聞こえますが、たとえば障害者手帳の取得とか、銀行預金額がいくらで年収がいくらとか、何歳以上であるとか、そういったヤツ。)
65歳以上になれば高齢者と言われますし、75歳以上で後期高齢者(例外有)とか言われますし、精神障害者保健福祉手帳を取得すれば精神障害者となります。(不思議ですね。病気があっても手帳をもっていないと制度の対象にならなかったりします)
その点、青年(ここでは主に12歳〜39歳ぐらいを想定)は、ひきこもりや貧困というカテゴリーに当てハマらなかったら、なんの制度もうけれんというわけです。セーフティ機能じゃないから。
なので、学校以外の青年育成の取り組みは、NPOや有志団体、各自治体によるところが多いかと思います。
なので、ばらつきが大きいです。
調べれば調べるほど、ざっくざっくと、いろいろ出てきます。
難しんですが、やはり青年育成って大切だなと思いました。
就職するも、すぐやめてしまう。
集団に入れない。
地域との交流の断絶。
それが、将来的に貧困や病気などのリスクをあげることにつながっています。
青少年の時って、意外に問題が無いようにみえたりするんですが、この時の学びや活動が、本人だけでなく、その地域にとっても大切だということが見えてきました。
問題は即席的にできあがらないみたいです。
私は、問題は個人にではなく、環境と、環境との相互作用にあると考えています。
例えば、仕事をすぐやめてしまう、という問題があったとしても、それは辞めてしまう人個人に全責任があるとは思いません。
現在の日本で求めれれている青年像はどんなものでしょうか。
経験的な所感になってしまうが、それは青年個人の本人の自主性が強く求められ、経済的自立の過度な強調ではと思います。
そういった強いプレッシャーに押し込まれ、選択性を失なっていることが、青年育成の問題ではないだろうかと、思うようになりました。
また、小さい頃から消費する文化に浸っているため、「消費者としての主体」となってしまうことも課題かと思います。
コンビニに行けば、お金さえ持っていれば子どもでもお客様として扱ってくれます。
(私は小さいこと、駄菓子屋にお菓子を買いに行ったときに、うっかり扉の敷居を踏んでしまいました。
そしたら、おばちゃんにめちぇめちゃ怒られました。)
スマホやパソコンで、遊びのニーズは満たされてしまう。
いつも、消費者としての生活なんですね。
何かを変えたり、創り出していったりする力が奪われていると思います。
なので、今後大切なのは、道をはみ出し、楽しむことが出来る若者の主体の形成と、それを受容できる環境整備ではないかと思っています。
(決して、経済的な教育を否定しているわけではなく、選択肢の狭まりが問題なのではと言いたいのです)
これかれら、もうすこしヒアリングを通じて、充実したプログラムができるように、コツコツやっていきたいと思います。
Posted by 峰政 裕一郎 at 20:00│Comments(0)
│おもったこと