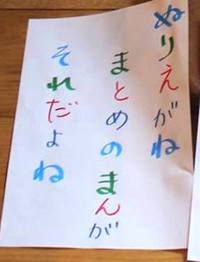2017年08月20日
けっこう発見が多い。コミュニケーションをみんなで振り返る方法と効果
実は、毎週土曜日の朝7時から朝活に参加しています。
朝活で何をしているのか。
「ファシリテーション」の勉強会です。
ファシリテーションって?
ざっくりいうと物事のプロセスに着目して、働きかけることで、会議をうまいこと進行したり、イベントや活動などに参加する人の力を引き出して最大限の成果を導き出したりする技術です。
もっとざっくりいいますと、めちぇめちぇうまい物事の進行役です。
ネットで「ファシリテーション」と検索すると沢山でてきますし、Amazonで検索してもアホほど本が出てきます。
8月19日の勉強会では、非言語メッセージに着目することをしました。
人が、人と関わり、コミュニケーションをとるときに、一見言葉による情報の交換をしているように思えますが、実は言葉以外のことでやり取りをしています。
例えば、顔の表情、視線、身振り、手振り、体の姿勢など、声のトーンや声質、物理的な距離、角度 また、服装や髪型、呼吸などなど。
一説によるとコミュニケーションにおける情報の割合は、言語に比べて非言語が6割とも、9割とも言われています。つまり、言葉で言った以上に、見た目の情報が人は影響を与えているということです。
少なくともコミュニケーション半分の以上は非言語メッセージが影響を与えています。
貧乏ゆすりしていたり、腕組みしている人には話しにくいし、座る距離が近すぎても遠すぎても話しにくいです。
そういった言葉ではないコミュニケーションを非言語的コミュニケーション(メッセージ)といいます。
ファシリテーター(あえて言えば会議の進行役)は、質問や声掛けだけでなく、身振りや手振り、表情、座る位置など、空間全体を駆使して最大限の成果を目指します。
でも、自分がどんな態度をしているかなんて、意外と意識しないものです。
なので、それを観察して振り返る練習をしたのです。
簡単に説明をすると、模擬会議をする人と、観察者にグループ分けをして、模擬会議を観察者が観察していくということをしました。
観察していて気になったことを付箋にどんどん書いていき、後でふり返りました。
ちなみに、まるで金魚鉢の内側にいる魚をみながら外から観察するこのような方法を、呼び方そのまま「フィッシュボウル」といいます。
わかりやすく解説しているサイトがこちらにありました。
観察者はファシリテーターに着目する人と、参加者に着目する人に分かれていただきました。
模擬会議はあくまでも模擬会議。
一通り行った後で、書いた付箋をみんなで張りだしてふり返りました。

そして、時系列ごとに振り返っていく。
この方法はいいですね。やっていて気がついたんですが、ビデオ録画より観察者の視点を雑談をしながら深めていくとが出来ますし、全体の共鳴感が高まります。
ふり返りでは、全体の沈黙、焦りといったことがどのような態度に出ているか、それに対してファシリテーターや会議参加者がどのように反応したり、対応したりしているかが見えてきました。
参加者やファシリテーターは、無意識のうちに感情を態度に出しているのがよくわかりました。
自信がなければ声のトーンや身振りにでていましたし、笑いを取れた後の表情なども。
色々学びになりましたが、こういった失敗してOKの場があるのは嬉しいと思いました。
会議でラクがしたいな、と思って参加している勉強会ですが、深いですね!
しかし、1人でシコシコ本を読んで学ぶより大分学びは大きいです。
朝7時から、濃い一時間でした。
朝活で何をしているのか。
「ファシリテーション」の勉強会です。
ファシリテーションって?
ざっくりいうと物事のプロセスに着目して、働きかけることで、会議をうまいこと進行したり、イベントや活動などに参加する人の力を引き出して最大限の成果を導き出したりする技術です。
もっとざっくりいいますと、めちぇめちぇうまい物事の進行役です。
ネットで「ファシリテーション」と検索すると沢山でてきますし、Amazonで検索してもアホほど本が出てきます。
8月19日の勉強会では、非言語メッセージに着目することをしました。
人が、人と関わり、コミュニケーションをとるときに、一見言葉による情報の交換をしているように思えますが、実は言葉以外のことでやり取りをしています。
例えば、顔の表情、視線、身振り、手振り、体の姿勢など、声のトーンや声質、物理的な距離、角度 また、服装や髪型、呼吸などなど。
一説によるとコミュニケーションにおける情報の割合は、言語に比べて非言語が6割とも、9割とも言われています。つまり、言葉で言った以上に、見た目の情報が人は影響を与えているということです。
少なくともコミュニケーション半分の以上は非言語メッセージが影響を与えています。
貧乏ゆすりしていたり、腕組みしている人には話しにくいし、座る距離が近すぎても遠すぎても話しにくいです。
そういった言葉ではないコミュニケーションを非言語的コミュニケーション(メッセージ)といいます。
ファシリテーター(あえて言えば会議の進行役)は、質問や声掛けだけでなく、身振りや手振り、表情、座る位置など、空間全体を駆使して最大限の成果を目指します。
でも、自分がどんな態度をしているかなんて、意外と意識しないものです。
なので、それを観察して振り返る練習をしたのです。
簡単に説明をすると、模擬会議をする人と、観察者にグループ分けをして、模擬会議を観察者が観察していくということをしました。
観察していて気になったことを付箋にどんどん書いていき、後でふり返りました。
ちなみに、まるで金魚鉢の内側にいる魚をみながら外から観察するこのような方法を、呼び方そのまま「フィッシュボウル」といいます。
わかりやすく解説しているサイトがこちらにありました。
観察者はファシリテーターに着目する人と、参加者に着目する人に分かれていただきました。
模擬会議はあくまでも模擬会議。
一通り行った後で、書いた付箋をみんなで張りだしてふり返りました。

そして、時系列ごとに振り返っていく。
この方法はいいですね。やっていて気がついたんですが、ビデオ録画より観察者の視点を雑談をしながら深めていくとが出来ますし、全体の共鳴感が高まります。
ふり返りでは、全体の沈黙、焦りといったことがどのような態度に出ているか、それに対してファシリテーターや会議参加者がどのように反応したり、対応したりしているかが見えてきました。
参加者やファシリテーターは、無意識のうちに感情を態度に出しているのがよくわかりました。
自信がなければ声のトーンや身振りにでていましたし、笑いを取れた後の表情なども。
色々学びになりましたが、こういった失敗してOKの場があるのは嬉しいと思いました。
会議でラクがしたいな、と思って参加している勉強会ですが、深いですね!
しかし、1人でシコシコ本を読んで学ぶより大分学びは大きいです。
朝7時から、濃い一時間でした。
この記事へのコメント
アニソン総選挙見た?
ゴッドノーズ、ギリギリ入ってたなぁ
ゴッドノーズ、ギリギリ入ってたなぁ
Posted by さくま at 2020年09月09日 02:30
at 2020年09月09日 02:30
 at 2020年09月09日 02:30
at 2020年09月09日 02:30